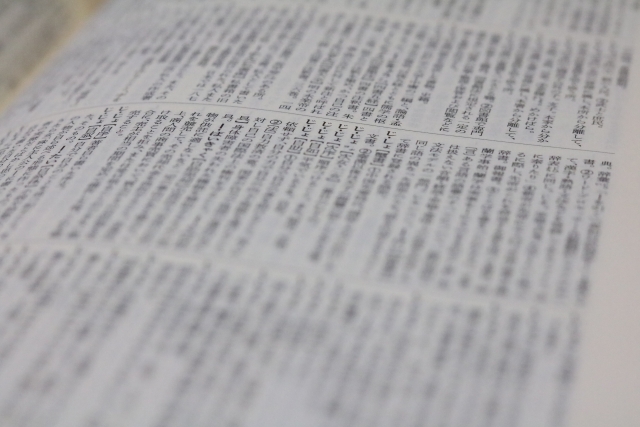妻子と別れ、孤独な日々を送るシナリオ・ライターは、幼い頃死別した父母とそっくりな夫婦に出逢った。こみあげてくる懐かしさ。心安らぐ不思議な団欒。しかし、年若い恋人は「もう決して彼らと逢わないで」と懇願した…。静かすぎる都会の一夏、異界の人々との交渉を、ファンタスティックに、鬼気迫る筆で描き出す、名手山田太一の新しい小説世界。第一回山本周五郎賞受賞作品。
(「BOOK」データベースより)

これは正直、原作よりも映画の方が、ずっと良い。
いつもは映像化されたものよりも原作を身贔屓にしがちですが、「異人たちとの夏」に関しては映画が勝ち。
ですので、映画観ましょう映画。以上。
・・・ごめんっ!これじゃ書評にならないっ!
本に戻りましょう。「異人たちとの夏」原作vs映画対決では映画の方が勝ってはいるものの、原作の小説だって、捨てたもんじゃないです。
夏の夕暮れの、打ち水をした後の涼しい風を感じることができる小説です。
「異人たちとの夏」の“異人”は、死者の意味。
その夏、主人公の前に突然あらわれたのは、主人公の父親と母親。父39歳。母35歳。
両親の享年を追い越して48歳になった主人公からすれば、頼れる大人であった父母のイメージと、あらためて巡り会った年下の“若い”父母の様子がまざりあって、死者との再会という混乱と共に、主人公の気持を揺り動かします。
そうよねえ。12歳の子供からしたら三十代の大人、しかも自分の親なんて、自分とは全く違う強大な存在に見えるけど。
四十代後半の現在から見れば、自分の親であっても“大人”だけでなく“人”として見える。
だけど、自分の心の根っこにある子供の気持ちが、年下の両親に甘えてもみたくなる。
親が死んでから30年以上たって、もう一度彼らに出会った時の、振り子のようにいったりきたりする気持ちがわかります。
私 さくらの母は、さくら十代の時に病死しておりまして。
もうすぐ私、母の享年に近くなってきているんですよ。もし我が母が「異人たちとの夏」のように今の私の目の前に現れたとしたら、私は同年代の母をどう見るんだろう?
父母が住まう田原町(浅草から地下鉄一駅)で、安らかで、ちょっとくすぐったいような、不思議な“異人たち”との交流を続ける主人公ですが、“異人”と触れ合うことは、主人公の肉体に影響を及ぼし始めます。
どうやら死者との交流は、耐えられないほどの負担がかかるらしい。当人の生命にかかわるほどに。
「父や母の意志じゃないと思う。ちがった世界との交流が、こういうことを必要とするんだ。おそらく父と母は、ぼくの衰弱を知らないんだ。ぼくと同じに衰弱が見えないんだ。きっとそうだ。そうじゃなければ、やつれたことを心配するはずだ」
「やさしいのね」
讃めているいい方ではなかった。ケイにはめずらしく皮肉がこめられていた。
恋人の説得もあり、主人公は両親との、改めて決別することを決めます。
息子が再度の、こんどこそ永遠の別れを告げた後に、親子3人で向かった浅草のすき焼き店。
そういえば、この時3人は何処のすき焼き屋に行ったのかしら?浅草にはすき焼き屋のお店がいっぱいあるんです。
3人が歩いていくのは(ちなみにユーレイでも他人に見えてますし、ご飯も食べられます)田原町から国際通り、途中の角で八目鰻を買って、六区の映画通り堅焼き煎餅を覗いて、ユーレイの身だから浅草寺は避けてすき焼き屋に行くならば、おそらく3人が行ったのはひさご通りの米久だな。すき焼き屋というより牛鍋屋という方がふさわしい、ボロっちい店。
1階の下足番の爺ぃに靴を預けて、2階のだだっ広い大広間に沢山の座卓。
ビールの泡と、グツグツ煮立つ肉と野菜と割り下の匂い。
最後に楽しく食事をしながら、最後の別れを惜しみたかったのに、残された時間はどんどん少なくなって。
「さよなら」
ほとんど見えない母がいった。
「あばよ」
父は見えなかった。
涙も出なかった。打ちのめされていた。
「さよなら」と小さくいった。
父も母も、たちまち跡かたもなく、箸と小鉢とビールのグラスと人形焼の袋と、お膳の汚れと皺のよった座布団だけがあった。
鍋が湯気を立てて煮えていた。
「ちっとも食べなかったじゃないか。ちっとも」
それから疲れがやって来た。
窓から入ってくる夕暮れの風の中、ひとり残される主人公。
この別れのシーンは、とても悲しい。
でも、とてもあたたかいです。
とはいえ、これが「異人たちとの夏」のラストシーンではなく、実は話がまだ続くんですが。
まあ最後のあれこれは、グリコのオマケみたいなもんだと思っておきましょう。
少なくとも私の中では、主人公の「夏」は、浅草の米久(と勝手に断定)2階の大広間で終わります。
私も夏の浅草で、私の異人に逢えたら嬉しいのだけれど。